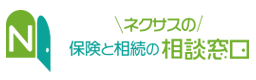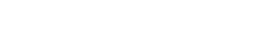2025年5月1日 / お役立ち情報 大切な資産を守り育てる:今を生き抜くための金融リテラシー

日本人の金融リテラシーは低め?
その現状と改善策を探る
こんにちは、茨城で地域密着型の保険・資産運用サービスを提供している「ネクサスの保険と相続の相談窓口」です。
政府は「貯蓄から投資へ」というスローガンのもと、NISA制度やiDeCoなどの活用を促進しており、投資や資産形成に対する関心も徐々に高まりつつあります。 こうした背景の中で、近年日本でも「金融リテラシー(お金に関する知識や判断力)」の重要性が改めて注目されるようになってきました。
しかし、いまだに「日本人は金融リテラシーが低い」と指摘される場面が少なくありません。
ではその理由は一体なぜ、どこに隠されているのでしょうか?
本稿では「金融リテラシー不足」の背景や現状を踏まえつつ、今後私たちがどのように知識を深めていくべきなのかを考察してみましょう。
リスク回避傾向と
「貯蓄は美徳」思想
国際比較で見える日本の課題
OECD(経済協力開発機構)などが実施する国際的な金融リテラシー調査によると、日本は他の先進国に比べて「金融知識」「金融行動」「金融態度」のすべての項目で平均を下回る傾向にあります。 特に、投資や保険の仕組みに対する理解度が低く、リスクを取ることへの抵抗感が強い点が課題とされています。
たとえばアメリカでは、高校の段階から株式市場やローン、クレジットカードの仕組みについて学ぶ機会がありますが、日本ではそうした金融教育がまだ十分に整備されていません。
「貯蓄は美徳」という価値観
日本では古くから「貯蓄は美徳」という価値観が根強く残っています。 戦後の高度経済成長期には、銀行預金の金利が高く、ただ預けておくだけで資産が増える時代が続きました。
この成功体験が、「投資=ギャンブル」「借金=悪」といった否定的なイメージを社会全体に根付かせてきたのです。
このような文化的背景も、日本人の金融リテラシーが伸び悩む要因の一つと考えられるでしょう。
金融教育の遅れと情報発信の偏り
課題の残る金融教育
日本では長年、学校教育において金融リテラシーの育成が軽視されてきました。
一応2022年度から高校の家庭科に「資産形成」に関する内容が導入されたものの、実践的な教育とは言いがたい内容から修正すべき課題は山積みである、といえます。
さらには指導を行う教師側の金融知識が十分でないことも多く、教育の質にもばらつきが生じている状態に…。
メディアによる情報の偏り
日本のメディアにおいても、投資や金融に関する正確で中立的な情報が十分に提供されていないケースが少なくありません。
株式投資や仮想通貨がセンセーショナルに取り上げられる一方で、長期的・分散的な資産形成の重要性は残念なことに軽視されがちです。
また、金融機関から発信される情報も商品の販売が目的となっている場合が多く、情報の中立性や信頼性に欠ける面があります。
「お金の話を避けたい」心理
日本人には「損をするくらいなら、何もしない方がよい」と考えるリスク回避傾向が特に強く見られます。
しかも「お金の話をするのは恥ずかしい」「がめつく思われたくない」といった文化的な心理ブロックも根深く、金融に関する話題自体を避けるてしまう傾向があります。
こうした感覚が、金融リテラシーを学び・実践する機会を大きく遠ざけてしまっているのです。
自己防衛に向けて
:「備え」の意識を持とう
現代社会において、金融リテラシー(お金に関する知識や判断力)は日常生活に欠かせないスキルとなっています。 たとえば給与の管理や税金の仕組み、住宅ローン、保険、年金、投資など…
どれも私たちの人生に直結するテーマであり、正しい知識がなければ不利益を被るリスクも大きくなってしまいます。
自己防衛として必須の金融知識
金融リテラシーは、単なる知識にとどまらず、自分の身を守る防御力としても機能します。 近年では「投資詐欺」や「仮想通貨詐欺」など、巧妙な手口による被害も急増中。
ですが基本的な金融知識があれば、こうしたリスクを見抜き、回避する力がしっかりと身につきます。
安定した資産形成と将来のために
少子高齢化や年金制度への不安が広がる中、老後に向けた資産形成はますます個人の責任となりつつあります。「貯蓄は美徳」に代表される銀行預金だけではインフレに対応できず、苦労して高めた資産価値が目減りしてしまう、という可能性も否定できません。
そのため、投資や資産運用の基礎知識を持ち、「自分の将来を自ら設計できる力」が求められているのです。
土台から育てる
:生涯を通じた「学び」の姿勢
①家庭ではじめる「お金の基本」
子どもにとって最初の金融教育の場は、家庭です。
お小遣いの管理や買い物の計画を通じて、「お金は労働の対価である」「限られた資源をどう使うか」といった基本的な金銭感覚を育むことができます。
また、親自身が金融について学ぶ姿勢を見せることで、子どもにとっても学びやすい環境が整います。
親子で一緒に学ぶことが、金融リテラシー向上の第一歩です。
②学校でも:実体験型授業の拡充
金融リテラシーはできるだけ早い段階からの教育が非常に効果的です。
そこでは知識を一方的に教えるのではなく、実生活に結びついた体験型の学習が求められることとなるでしょう。
たとえば、仮想の家計予算を組んで収支を管理する授業や、実際の企業の株価を観察するプロジェクトなどを通じて、楽しみながら学べる環境を整えることが重要です。
③ 社会人でも:メディア活用を積極的に
子どもに限らず、もちろん大人でも知識を蓄えることは難しくありません。
近年は、自治体や企業によるセミナー、YouTube・SNSでのわかりやすい解説動画、さらには無料のオンライン講座など、さまざまな学習機会が広がっています。
特に初心者には、インフルエンサーや専門家が発信する「視覚的で実践的な情報」が入り口として効果的です。
④学びは「実践にこそ」あり!
真に金融リテラシーを高めたいと思うならば、実際に少額から投資や資産運用を始めてみるのも効果的でしょう。
NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用し、長期・分散・積立の原則に基づいた運用を通じて、経済の動きやリスク管理を“肌で”理解することができます。
初めから「成功」や「正解」を求めるのではなく、「小さな経験を積む」姿勢が重要なのです。
知識で守る大切な資産
:身近なところからお金を学ぼう!
日本人の金融リテラシーが低いとされる背景には、教育制度の遅れや文化的な価値観、さらには正確な情報へのアクセス不足といった複数の要因が絡んでいます。
しかし今後の流れとして「知っておくとお得」ではなく「知らないと損をする」、つまり金融知識への理解が必須となる時代が必ずやってくることでしょう。
多くの情報が錯綜する、これからの社会を生き抜くためには、教育の在り方を見直すと同時に、私たち一人ひとりが主体的に学び続ける姿勢が求められます。
時間や場所を問わず、まずは身近なお金の使い方から見直すことから「あなたの金融リテラシー」は始まるのです。
自分の未来を守るために、そして安心して選択できる人生のために…
これからも「お金の知識」を自分のものにしていきましょう!
お読みいただきありがとうございます。
もし「お金の知識をもっと学びたい」
「将来に備えたお金の相談を」と思ったら…
茨城で地域密着型の保険・資産運用サービスを提供しているネクサスの保険と相続の相談窓口では、お金のプロが教える定期的なマネーセミナーやお金の勉強会を随時開催しております。分かりやすく丁寧に、初心者の方でももちろん大歓迎!
ぜひお気軽に参加ください。