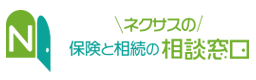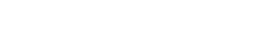2025年5月1日 / お役立ち情報 金融機関の利益は「悪」なのか?今だからこそ考えたい「金融リテラシー」のお話

「金融機関が得ならお客様は損」
それって本当?
こんにちは、茨城で地域密着型の保険・資産運用サービスを提供している「ネクサスの保険と相続の相談窓口」です。
「金融機関が儲かっているということは、私たち利用者が損をしているのでは?」
そんな疑問を抱いたことがある経験が、皆さまの中にもあるかもしれません。
銀行や証券会社、保険会社などの金融機関は、私たちの資産形成や生活設計に深く関わるサービスを提供しています。
しかし一方で、「知らないうちに手数料が差し引かれていた」「勧められた商品が思ったほどの成果を出さなかった」といった経験から、不信感を抱く人が少なくないのも現実です。
ですが本当に、「金融機関が得をする(利益を得る)=お客様が損をする」構図は成り立つのでしょうか?
今回は金融機関のビジネスモデルや商品設計の仕組み、そして顧客との関係性といった観点から、「損得の構図の真偽」を紐解いていきましょう。
利ざや・手数料・運用益…金融機関の主な収益源を理解しよう
まずはじめに、金融機関がどのように利益を上げているのかを理解することが重要です。
以下3つの代表的な収益源を確認してみましょう。
-
利ざや収益(銀行)
銀行は、預金者から低金利でお金を集め、それを企業や個人に対して高金利で貸し出すことで「利ざや(スプレッド)」を得ています。
例えば、預金に0.001%の利息を支払いながら、融資では1.0%の金利を設定すれば、その差額0.999%が銀行の利益となります。 -
手数料収益(証券会社・保険会社など)
証券会社や保険会社では、株式や投資信託、保険商品などを販売する際に、以下のような手数料を受け取ることで収益を得ています。■販売手数料(商品購入時)
■運用手数料や信託報酬(継続保有中)これらの手数料は、利用者が意識しづらい「見えにくいコスト」となっているケースも少なくありません。
-
資産運用益(自己勘定取引)
一部の金融機関では、自社の資金を使って株式や債券、為替市場などで運用を行い、その運用益を利益としています。
これを「自己勘定取引」と呼びます。
このように金融機関は「お金の仲介役」として機能し、利ざやや手数料、運用益といった3つの収益源から成るビジネスモデルを構築しています。
また一部においては自社で株式や債券、為替などに投資を行い、運用益を得るところもあります。
「儲かる=悪」ではない?金融機関の利益と顧客の関係を考える
では本題に戻りましょう。冒頭でも述べたように、本当に「金融機関が利益を上げるほど、私たちは損をしている」という構図は正しいのでしょうか。
その疑問に対する答えは…「金融機関の利益」と「顧客の損得」は必ずしもトレードオフ(二律背反)の関係にあるとは限らない、ということです。
たとえば、銀行が企業に融資を行い、そこから利息収入を得たとします。
その資金を活用して企業が成長すれば、新たな雇用が生まれ、地域経済が活性化し、社会全体にとってもプラスになるでしょう。
つまり結果として、顧客である企業やその地域社会も広く恩恵を受けることができるのです。
また、投資信託等の金融商品についても例外ではありません。
金融機関が手数料を受け取ることに対して、顧客には資産運用のチャンスが提供されています。
したがって運用が上手くいけばいくほど、顧客自身も利益を得ることが可能なのです。
この2つの例からもお分かりいただけるように、金融機関が利益を上げること自体は決して「悪」ではありません。
問題なのは、金融機関が自らの利益を優先するあまり、顧客の利益を犠牲にしてしまうケースなのです。
次の項目では、こうした“利益相反”の実例について詳しく解説します。
利益重視で販売される
金融商品の裏側とは…
金融機関が自社の利益を優先しすぎるあまり、顧客に不利益を与えてしまう“利益相反”。
ここでは、実際に起きがちな3つの代表事例をご紹介します。
高コストな投資信託の販売
投資信託には以下のような費用がかかります。
-
購入時手数料
-
信託報酬(運用中の手数料)
-
信託財産留保額(解約時にかかる費用)
中には「販売手数料3%」「信託報酬1.5%」といった高コストな商品も存在します。
こうした商品は、証券会社や銀行にとって手数料収入が大きいため、積極的に販売されがちです。
しかし、顧客にとっては手数料負担が大きく、運用益が思うように出にくい場合が大半。
その結果、「売る側が儲かり、買う側は損をする」という不健全な構図になってしまうのです。
ノルマ重視の保険販売
保険営業の現場では、契約件数や売上目標などのノルマが設定されることがあります。
そのプレッシャーから一部の営業担当者が、「本当に顧客に合った保険」ではなく、
-
手数料が高い
-
売りやすい
といった保険商品を優先して勧めてしまうケースがあります。
とくに、外貨建て保険や変額保険などは、仕組みが複雑でリスクが高いにもかかわらず、「利回りが良い」「将来の安心に繋がる」といった説明で販売され、トラブルの原因となることもあります。
預金金利と貸出金利のギャップ
預金者に提供される金利が0.001%など非常に低い一方で、個人ローンやカードローンでは年10%を超える金利が設定されていることがあります。
このように、低金利で資金を集め、高金利で貸し出すことで得られる利ざやは、銀行の主要な利益源です。
もちろん、銀行経営にとって重要な仕組みではありますが、預金者からは「預けてもお金がほとんど増えない」といった不満の声が上がることも少なくありません。
顧客の利益を守る
「顧客本位」の時代へ
こうした問題を受け、近年注目されているのが「フィデューシャリー・デューティー(受託者責任)」という考え方です。
これは、金融機関が顧客の最善の利益を優先して行動すべきだという倫理原則であり、欧米をはじめ日本でも重要視されている行動指針でもあります。
日本においては金融庁が「顧客本位の業務運営に関する原則」を掲げ、以下のような改善を金融機関に求めています。
-
販売手数料の透明化
-
利益相反の開示
-
営業方針・評価制度の見直し
これにより、顧客との信頼関係を損なわず、持続的な金融サービスが提供されることを目指しているのです。
さらに近年では、インターネット証券やロボアドバイザー、フィンテック企業といった新たなプレイヤーも登場。
これらのサービスは「低コスト」「高い透明性」「中立的な立場」を強みとしながらも、従来の金融機関に対する新たな選択肢として台頭しつつあります。
顧客本位の姿勢は、より一層強く金融業界に浸透してゆくこととなるでしょう。
あなたの資産はあなたが守る!
今こそ必要な金融リテラシー
繰り返しますが、金融機関が利益を上げること自体が悪いわけではありません。
むしろ、適切なサービスの対価として収益を得ることは、健全な経営の証でもあります。
しかし問題となるのは、その利益の裏で顧客が不利益を被っている場合があること。
「自分が損」を被らないためにも、これからの資産運用では「受け身」ではなく主体的に判断する姿勢が必要となるのです。
ですが「どんなところに気を付ければいいの?」と悩んでしまう、そんなシーンもあるかもしれません。
そこでもし迷われてしまった時は、以下のような行動を意識してみてください。
自分の資産を守る力=金融リテラシーを着実に高めることができるできるでしょう。
-
商品の手数料やリスク構造を事前にしっかり確認する
-
「勧められたから」ではなく、自分が納得して選ぶ
-
複数の金融機関や商品を比較し、信頼できるパートナーを選ぶ
-
不明点は遠慮なく質問し、わかるまで説明を求める
今後ますます重要になるのは、情報を正しく理解し、自分自身で判断する力です。
変化の激しい時代だからこそ、金融リテラシーを身につけることが、自分の資産と人生を守る第一歩になるのです。
金融機関とお客様、
両者が納得できる関係を目指して
「金融機関が得をすると、お客様が損をする」――そんな構図は、確かに一部のサービスにおいて存在しています。
しかし、すべての金融サービスがそのような関係性にあるわけではありません。
金融機関の利益と顧客の利益が両立することは十分に可能です。
そのためにも、金融機関側は倫理観・説明責任・透明性、そして利用者側は情報収集力と判断力を、互いに重視しあうべきなのです。
私たち一人ひとりが「自ら選び、納得して使う」姿勢を持つことが、健全で信頼される金融のあり方を支える力となります。
茨城県の保険代理店「ネクサスの保険と相続の相談窓口」では、「金融機関の常識は、世間の非常識」を合言葉に、お客様一人ひとりとの信頼関係を何より大切にしています。
地域に根ざした存在として、末永く寄り添えるパートナーを目指し、困ったときに頼れる“金融のかかりつけ医”であり続けたいと願っています。
保険やお金に関する疑問や不安がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
「ネクサスの保険と相続の相談窓口」は水戸・ひたちなか・鹿嶋に店舗ございます。
オンラインでのご予約も受け付けておりますので、ぜひお近くの店舗をお探しくださいませ!