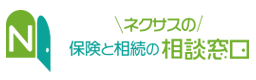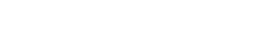2025年4月22日 / お役立ち情報 お金持ちほど注意が必要?茨城の“稼ぐ人”のための相続について

茨城で地域密着型の保険・資産運用サービスを提供している「ネクサスの保険と相続の相談窓口」です。
今回は、「なぜ今、相続対策が必要なのか?」をテーマに、現代の相続事情や、今からできる備えについてわかりやすく解説します。ご家族を守るために、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ今、相続対策が必要なのか?
「相続は資産家の問題」と思われがちですが、現代では年収800万円以上の方も相続対策を怠ると、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
特に茨城のように、不動産や土地を所有しているご家庭では、評価額が高くなりがちです。実際の生活感覚では「それほどお金持ちではない」と感じていても、いざ相続となると相続税の課税対象になることは珍しくありません。
さらに、高収入世帯では「家族間で話さなくても分かり合えている」と思いがちですが、コミュニケーションの不足が“争族”を招く一因となるケースも多いのです。
だからこそ、「うちは大丈夫」と思っている今こそが、備えるべきタイミングなのです。
相続の基本をおさえよう
まず、相続とは「ある人が亡くなったとき、その人の財産や義務(借金など)を相続人が引き継ぐこと」です。
相続人とは、原則として配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などの血縁者です。相続には「法定相続」と「遺言による相続」があります。遺言がなければ民法上のルールに基づいて自動的に分割されます。
相続の対象となる財産とは?
相続対象になる財産には以下のようなものがあります:
不動産(土地・建物)
預貯金
株式や投資信託
車や貴金属などの動産
生命保険金(場合による)
一方で、借金やローンなどの負債も相続の対象です。
さらに、遺言書があれば原則としてその内容が優先されます。ただし、「遺留分(最低限の取り分)」が侵害されている場合は、トラブルの原因になることも。
“もめる相続”の典型例
実際の現場では、どのような相続でもめてしまうのでしょうか?
① 遺言書がない・不明確
「親が何も書き残さず亡くなった」「メモのような遺言書しかなかった」など、正式な遺言がないと、相続人同士で話し合わなければなりません。感情的になりやすく、冷静な話し合いが難航しやすいです。
② 財産の内容が不透明
「どこにどれだけの預金があるのか分からない」「不動産の名義が昔のまま」など、財産の見える化がされていないと、手続きに時間がかかり、不信感も募ります。
③ 不公平感
「長男が多くもらった」「介護してきたのに遺産は平等」など、相続人の間で“納得感”がないと争いになりやすいです。
④ コミュニケーション不足
高収入世帯では「言わなくても分かる」と思いがちですが、きちんと話し合っておかないと、誤解や思い込みが元でトラブルになります。
円満相続のコツ:今からできること
「うちは大丈夫」と思っている人ほど、今すぐ始めてほしいのが相続準備です。以下の4つのコツを意識することで、争いを防ぎ、家族全員が納得できる相続が実現できます。
コツ① 推測で判断せず、事実をもとに行動する
「たぶん、親は自分に多く残してくれるだろう」「弟は納得しているはず」など、思い込みで話を進めないことが重要です。法的なルールを確認し、事実ベースで整理しましょう。
コツ② 「公式ルール」で論点整理をする
相続には法律上の決まりがあります。誰がどれだけもらえるのか、どのような手続きが必要なのかを、専門家の力も借りて整理することで、感情論を避けることができます。
コツ③ 相続人同士のコミュニケーションを大切にする
早めに家族で話し合い、相続への共通認識を持つことが重要です。「争わないための準備」として話すことで、感情的な対立を避けることができます。
コツ④ 専門家と連携し、“想定外”を減らす
税理士や司法書士、行政書士、FPなどの専門家のサポートを受けることで、見落としや誤解を最小限に抑えることができます。特に不動産や法人を所有している場合は、相続税対策の視点も欠かせません。
早めの対策が“家族を守るカギ”
相続は、「誰かが亡くなってから考えるもの」ではありません。とくに年収800万円以上あるような高収入層にとっては、財産の規模や税金の影響、家族関係の複雑さなどから、事前に備えておくべき要素が多く存在します。
茨城のように不動産価値が安定している地域では、予想以上に財産評価額が高くなるケースも多いため要注意です。
家族を大切に思うからこそ、今、相続についてきちんと向き合うことが、結果的に“争いのない未来”をつくる第一歩となります。
相続税の総額の計算
まず、相続人等が遺産をどのように分割したかに関係なく、相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算します。次に、この各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を合計したものが相続税の総額となります。
各人の納付すべき相続税額の計算
相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分して計算した金額が各人ごとの相続税額となります。
なお、相続や遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
最後に、各人ごとの相続税額から、後述する「配偶者の税額軽減額」、「未成年者控除額」、「障害者控除額」などの税額控除の額を差し引いた金額が、各人の納付すべき相続税額となります。

| 法定相続分に応じた所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続対策をするうえで大切なこと
相続に関するさまざまな心配ごとをなくそうと考える余り、過度な対策とならないように注意しましょう。例えば、生前贈与をしすぎて自分と家族の生活に支障が出るようであれば本末転倒です。ここでは、相続対策をするうえで大切な3つのポイントを心得ておきましょう。
➀生存中の生活費の確保もしておく
②早めに行動する計画を立てる
③税理士やFPなどの専門家に相談する
不動産の購入など、多額の資金を要する対策方法を検討する場合には、生存中の生活への負担も考えながら行いましょう。これから築く財産も含め、「生存中に必要な財産」「遺す財産」を意識しながら金融機関や金融商品を選んでください。
「年齢に関係なく、誰もが相続対策を行いたい」と思いますが、どうしても後回しにしがち・・・
相続はいつ起こるか分かりません。
そう考えると、ただ早めに検討するだけでなく、実際に行動していくことが大切です。対策方法によっては、時間がかかるかもしれません。また、贈与のように相続発生時と時期が近いとせっかくの対策が効果を生み出せない場合もあります。加えて、相続対策には専門的な知識が必要です。自己判断で難しいと感じる場合は、迷わず税理士などの専門家に相談し、アドバイスを受けましょう。
自分には関係ないと思わず、早めに検討・対策を
今回の例は、相続対策の一例です。
相続対策は、たくさん財産がある場合だけに行うものではなく、財産額の多少や年齢にかかわらず、誰にとっても必要です。決して他人ごとではなく、「自分ごと」として取り組んでください。
また、相続対策は心配ごとに応じた対策がたくさんあるため、事前に手立てを打ち、相続に関する心配ごとを軽減させることが重要です。もし、自分だけで相続対策が難しいと感じる場合は、税理士や相続に詳しいFPなどの専門家の力も借りながら、いつ起こるか分からない相続に備えて、早めに対策を始めましょう。
ネクサスの保険と相続の相談窓口では、皆さまが安心して相談できる環境づくりを大切にしています。
相続や資産運用に関する不安や疑問に、最適なアドバイスをご提供いたします。
「うちは大丈夫かな?」と思った今が、準備を始めるベストタイミングです。ぜひお気軽にご相談ください!